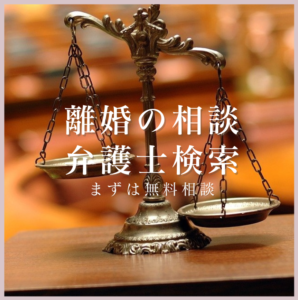【はじめに】

婚姻費用って、正直なところ最初はよく分からなかったんです。私も最初にこの言葉を耳にしたとき、「それって何のこと?」と思いました。でも、調べていくうちに、「あ、これって意外と大事なことなんだな」と気づきました。というのも、夫婦って一緒に生活している間、生活費も分け合うべきだっていう考え方があるんですね。
たとえば、「別居中だけど生活費が足りない」「収入が少なくて困っている」なんて状況、けっこうよくある話です。そんなときに頼りになるのがこの婚姻費用なんです。知らないと損する制度のひとつだと思います。
【婚姻費用とは?】

難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言えば「別居中でも夫婦で生活費を分担しようね」というルールです。民法っていう法律でそう決まってるんですよ。私は最初、そんなことまで法律で決まってるなんてびっくりしました。
ちなみに、こういう話って役所の相談窓口なんかでも聞けるみたいです。実際に子どもがいるご家庭なんかでは、この婚姻費用があるかないかで生活がかなり違ってくると思います。夫婦の片方だけが生活費を全部負担するのは、やっぱり無理がありますよね。
【婚姻費用の計算方法】

計算の仕方って難しそうに見えますけど、実はけっこうシンプルな仕組みです。ざっくり言うと、「お互いの収入を比べて、それぞれどれくらい負担すべきか」を計算するんです。
私が見た例では、年収600万円の夫と300万円の妻で、子どもが中学生1人いる家庭だと、月にだいたい10万円くらいの婚姻費用が目安になることもあるそうです。数字だけ聞くと大きく感じますが、子どもがいれば食費も教育費もかかるので、現実的な金額かもしれませんね。
【新旧算定表の違い】
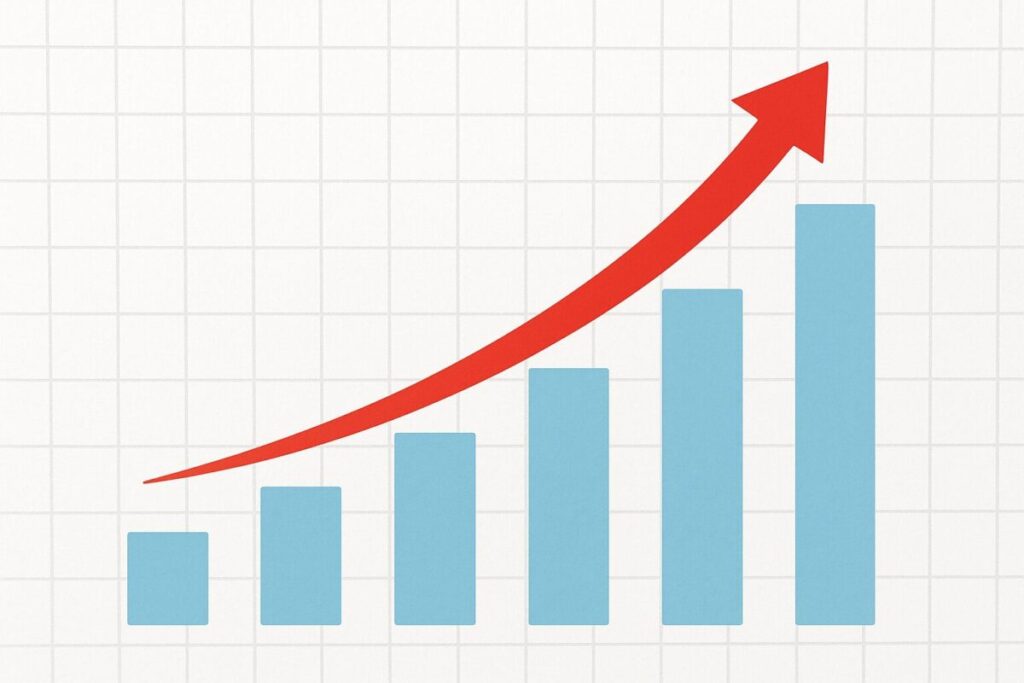
令和になってから、この婚姻費用の算定表も新しくなったそうです。私も見比べてみたんですが、確かに新しい表のほうが金額が高く出る傾向があります。物価が上がっているからっていうのが理由みたいです。
古い表を使って計算すると少なめになっちゃうこともあるので、できれば新しい表を使うほうが安心です。ネットで検索すると、「令和版」ってついてる表も見つけられますよ。
【自動計算ツールの活用法】
これ、めちゃくちゃ便利でした!年収とか子どもの年齢を入れるだけで、婚姻費用の目安をすぐに教えてくれるんです。私も試してみたんですが、「だいたいこれくらいか〜」って感じでイメージが湧きました。
しかも無料で使えるツールが多いので、気軽に試せるのが嬉しいですね。私の場合、計算した金額をもとに弁護士さんに相談したら、すごくスムーズに話が進みました。
【請求の流れ】

実際に婚姻費用を請求するには、まずは相手と話し合いをしてみるのが最初のステップです。これでうまくまとまればラッキーですが、なかなかそう簡単にはいかないこともありますよね。
そういうときは、家庭裁判所で「調停」を申し立てることができます。これは第三者が間に入ってくれて話し合う場です。もしそれでも決まらなかったら、「審判」という手続きで裁判所が決めてくれます。
【Q&A】
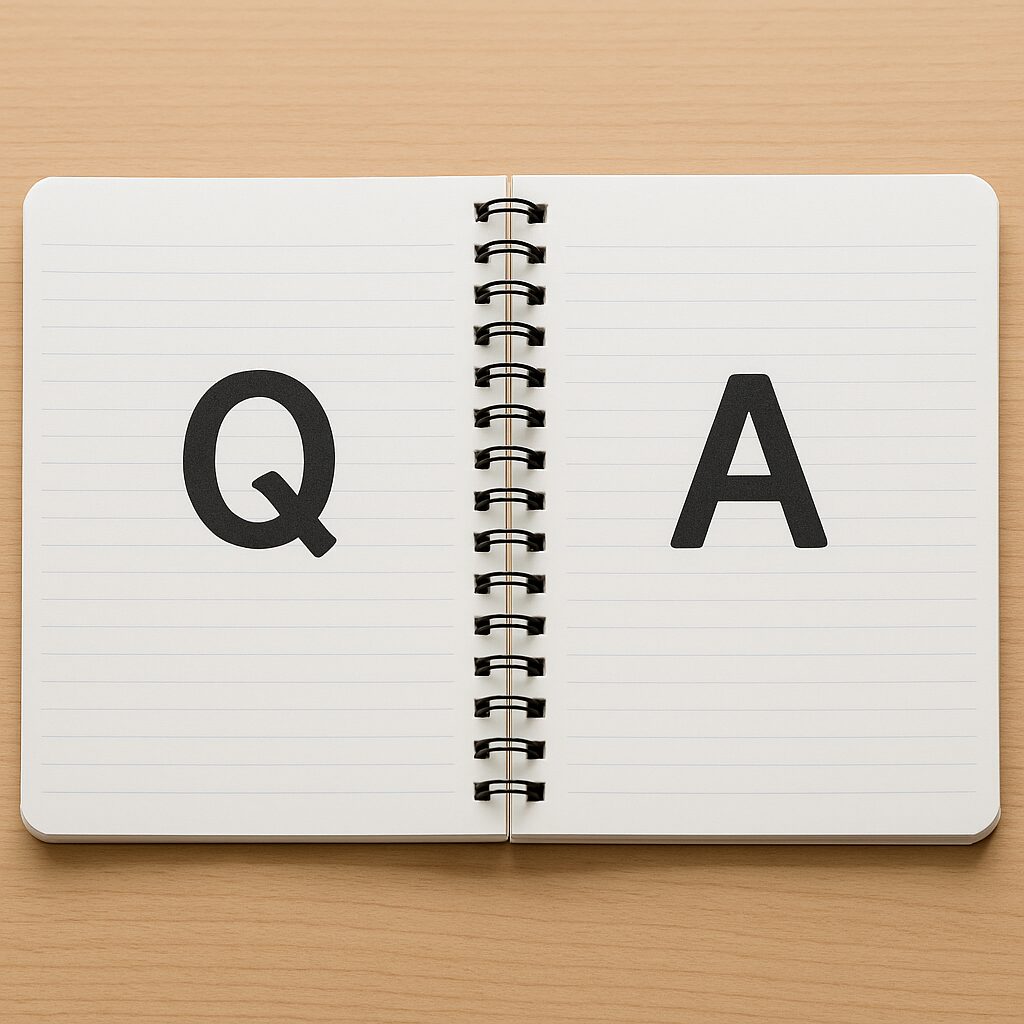
Q. 子どもがいない場合でも婚姻費用はもらえるの? A. はい、大丈夫です!子どもがいなくても、夫婦で生活費を分け合うルールは同じなので、もらえる可能性があります。
Q. 無職でも請求できるの? A. できます!でも、裁判所は「働ける可能性があるか」も見てくるので、全く収入がない場合でも、何かしら働けると判断されたら、ちょっと考慮されるかもしれません。
Q. 相手が全然話を聞いてくれないんだけど…? A. そんなときは家庭裁判所を頼るのが一番です。弁護士さんにお願いすることもできますし、あまり一人で抱え込まないのが大事ですよ。
【まとめ】

婚姻費用って、言葉だけ聞くと堅そうですけど、実は私たちの暮らしにすごく関係のある制度なんだなと実感しています。特に別居中や離婚を考えている人にとっては、知っておくだけでも安心感が違います。
「難しそう」と思って最初の一歩が踏み出せない人も多いかもしれませんが、実際にやってみると意外と簡単だったりします。まずは自分の状況を整理して、ツールを使ってみることから始めてみませんか?